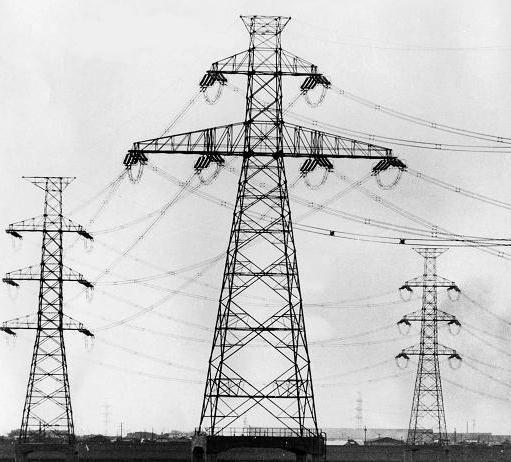2.電線・地線設計The design of conductor and ground wire
電線設計の基本は、計画された電力を、電線の劣化を起こさず低損失で送電させることである。
(1)電気的性能The electrical performance of conductor
求められる性能を列記すれば次の通りである。
定められた常時の送電電流を、定められた電線温度以下で送電し、耐用年数内では性能劣化しないこと。
同一の送電系統の他の送電回線が、事故などで送電不能になったとき、短時間ではあるが通常より多くの電流を送電せざるを得ないときでも、定められた電線温度以下であること。
常時の送電電圧で、異常放電をせず、送電線に近接した場所でラジオ受信に雑音障害を与えないこと。
(2)機械的性能The mechanical performance of conductor
電線は過酷な気象条件にも十分な強度を保ち、電線温度が上昇し弛度が増加しても規定の地上高を確保するよう、下記の条件を考慮して張る。
台風などの強風に耐えること。
電線に着氷したり、着雪したときの重量および風圧荷重、そのときの異常電線動揺(スリートジャンプ、ギャロッツピングなど)に耐えること。
規定の電線温度上昇時、規定の地上高を確保すること。
ごく弱い風(微風)のとき発生する電線振動を抑制し、それに耐えること。
海岸付近の塩分、工場地帯の有害汚損空気に耐えること。
(3)電線の選定The choice of the kind of conductor
送電線が建設運用され約110年が経つ。
特に大電流を流したい場合は、後述の耐熱性能を向上させた「鋼心耐熱アルミ合金より線(TACSR)」を選定し、かつ太い電線を使用することがあり、使用実績としては TACSR 1520m㎡(外径52.8mm、許容電流約3,000A)を採用した例がある。
ACSRは、連続して電流が流れ、電線温度が上昇しても引っ張り強度が低下しないよう、90℃以下の温度で運転出来る太さの電線を選定する。
電線の撚り方向
さて、電線の最外相の撚り方向には右写真のように2種類がある。
(4)地線の選定The choice of the kind of ground wire
地線、正確には架空地線は、落雷時、電線(電力線)に雷が直撃しないよう、支持物の最上段に配置し、地線に落雷させて雷電流を大地に流す役目をしている。
(5)架線設計Stringing design
電線をあまり緩く張ると、支持物が異常に高くなり、建設費が高く不経済になり、逆にあまりきつく張れば強い特殊電線が必要となり、また頑丈な支持物を建設しなければならず建設費がかさむ。
台風や着氷雪時の過酷な気象条件でも、規定の張力内に収める。(張力の条件)
上記の条件を満足するよう、張った電線の弛みは、規定の負荷電流が流れ電線温度が上昇して弛度が増大しても、電線地上高は規定値以上に確保され、電線直下の工作物等との安全離隔を確保する(支持物高さを決める)。(弛度の条件)
さらに、送電線が健全な状態で運転出来るよう、送電線周囲の状況を常に監視・管理することが大切である。2003年8月14日に発生した北米東部とカナダの大停電 は、送電線に過大電流が流れ電線弛度が増大し、線下の樹木に電線が接触してフラッシオーバしたのが最初の原因だったが、架線設計および線下の樹木管理に問題があったためである。
電線の許容張力
最大風速条件
着氷雪条件
経過地の気温
電線の許容温度
ⅰ.電線の許容張力
長期にわたって電線の機械的性能を劣化させないため、電線の抗張荷重(引っ張り強さ)に対し、安全率をACSRの場合は2.5以上とし、許容張力を定める。
ⅱ.最大風速条件(高温季荷重)
電線に真横から風が当たると、電線は横に振れるとともに風圧で電線張力が増加する。「高温季荷重」 という。
ⅲ.着氷雪条件(低温季荷重)
冬季は、経過地にもよるが、日本列島の大部分の地域では、電線に着雪や着氷することを考慮して架線設計をする。「低温季荷重」 という。
ⅳ.経過地の気温
電線架線に際しては、経過地の最高気温と最低気温を確実に把握する。
ⅴ.電線の許容温度
電線温度が経過地の最高気温(関東以西では45℃)の時の無風状態での弛(たる)みで、規定の電線地上高が確保出来るように支持物の高さを決めるのが、弛度設計の基本であると前述した。
(6)電線付属品(気象条件対策用)The accessories (weather measures) of conductor
電線は、長年にわたり過酷な気象条件に曝されるが、それでも性能を劣化させないで良好に機能を発揮させなければならない。
ⅰ.風による電線振動対策
風速数m程度の微風が電線に直角に一様にあたると、電線の後方(風下側)でカルマン渦が発生し、電線に上下方向の力が働く。
a.トーショナルダンパ
鋼線の両端に錘をつけたもので、電線支持点から振動ループ長の1/2~1/3の位置に取付け、電線の振動エネルギーを吸収し、振動を防止する。
b.パイプレスダンパ
このダンパは、ストックブリッジダンパの重錘構造を簡略化し、かつ、ダンパケーブルに捻れを生じるように棒状重錘が偏心して固定されている。
c.べートダンパ
ベートダンパは、電線に添え線式に別の電線をほぼ無張力で取り付け、微風振動エネルギーを吸収させる。
d.ストックブリッジダンパ
鋼線の両端に錘を取り付けたもので、考案者のStockbridgeの名前をとって名付けられた。
e.アーマーロッド
また、電線の支持点の補強をするものとして、アーマーロッドが使用される。
ⅱ.着雪対策
a.難着雪リング
冬季に、電線に雪が異常に多く付着(直径数㎝の電線に10㎝以上の厚さの雪が付くこともある。さらにそれがべタ雪の場合氷状になることがある)すると、過大な張力が生じ、電線が切れたり、場合によっては支持物が倒壊することがある。
b.捻れ防止カウンタウエイト
また、電線 に着雪した場合に電線が回転し、円筒形状に次第に厚く着雪するのを防ぐため、電線に錘(カウンタウエイト)を取付け回転・捻れを抑制し着雪を防止する、捻れ防止カウンタウエイトを取り付ける。
ⅲ.着氷対策(ギャロッピング対策)
冬季に電線に氷が付着することがある。この着氷現象は地域的条件が大きく左右することが知られている。
注 ギャロッピング現象動画追記掲載(2013.01.16)
ギャロッピング現象については、発生するタイミングを的確に予測し観測することが難しいため、発生チャンスを捉え撮影・記録し、且つ公開されているものは極めて希であるが、カナダのマニトバ水力発電会社のホームページに載せてあるのを見つけたので紹介する。http://www.hydro.mb.ca/corporate/facilities/galloping_powerlines.shtml
なお、このギャロッピング現象は、着氷現象が無くても、着雪後に雨に変って付着した雪が氷状(シャーベット状)に変化したときなど、非対称着雪状態になったときに強風で発生することもある。A:多導体の単導体化: 多導体より単導体の方がギャロッピングを発生しにくく対策として有効であるB:特殊電線の採用: 電線断面および表面形状について、着氷してもギャロッピングの発生しにくい空力特性のものにするC:鉄塔装柱を工夫: ギャロッピング発生時の電線運動許容空間を確保するA: の多導体を単導体にする対策は、2導体を単導体に変更した例として蔵王山の近くを経過する275KV送電線、および奥利根山岳地帯を経過する275KV送電線での対策例がある。B: はほとんど採用されていない。C: は水平配列化および線間距離拡大の例がある。A:相間スペーサ B:捻回抑制装置(TCD:Torsional Control Device) C:スパイラルロッド(空力特性制御) D:偏心重量錘(位相制御) E:回転自在型(ルーズ)スペーサ F:フリクションダンパ
a.相間スペーサ
径間の途中で、電線と電線間に絶縁物で出来た棒状の、相間スペーサを取り付けるものである。
右に275KV4導体に使用された例を掲載しているが、500KVでは相間スペーサが長尺になり機械的強度を確保することが難しく、その限界は275KV迄であろう。
b.回転自在型(ルーズ)スペーサ
超高圧多導体送電線では、多導体用スペーサにギャロッピング現象抑制効果をもたせた「回転自在型(ルーズ)スペーサ」を採用し、ギャロッピング抑止効果を発揮させる送電線が次第に建設されている。
右写真は、275KV2導体送電線への、ルーズスペーサ適用例である。
c.回転自在型(ルーズ)スペーサ+偏心重量
超高圧多導体では、多導体用スペーサにギャロッピング現象抑制効果をもたせた「回転自在型(ルーズ)スペーサ」と、「偏心重量錘」を組み合わせて取り付け、ギャロッピング抑止効果を発揮させた送電線も建設されている。
d.捻回抑制装置(ギャロッピング防止ダンパ)
このダンパは、電線と重錘をケーブル(亜鉛メッキ鋼線)で連結し、反力で大きな捻回トルクを発生させ、(錘の位相を、電線変位に対して遅らせ)、大きなエネルギー消費を生じさせてギャロッピングを抑止するものである。
(7)電線付属品(機械的・電気的機能発揮用)The accessories (mechanical and electrical measures) of conductor
機械的・電気的機能を発揮するための付属品としては、・多導体用スペーサ ・直線スリーブ ・引留クランプ ・ジャンパー装置
ⅰ.多導体用スペーサ
多導体の送電線では、同一相内の電線を密着させず、電線相互間を数十cm以上離して正多角形に配置し、風による横振れがあっても規定の間隔を保持し、互いに接触しないよう、「スペーサ」と称する金具を数十mおきに使用する。
a.2導体スペーサ
右の2導体スペーサ写真は、電圧:275KV、電線:ACSR330m㎡、素導体間隔:400mm
右の2導体スペーサ写真は、電圧:275KV、電線:TACSR1520m㎡、素導体間隔:1000mm
右は、垂直2導体スペーサ写真である。
b.3導体スペーサ
右の3導体スペーサ写真は、電圧:500KV、電線:TACSR810m㎡、素導体間隔:600mm
c.4導体スペーサ
右の4導体スペーサ写真は、電圧:275KV、電線:ACSR410m㎡、素導体間隔:400mm
d.6導体スペーサ
右の6導体スペーサ写真は、電圧:500KV、電線:TACSR810m㎡、素導体間隔:500mm
右の大束径6導体スペーサ写真は、電圧:500KV、電線:TACSR410m㎡、素導体間隔:800mm
e.8導体スペーサ
右の8導体スペーサ写真は、電圧:1000KV、電線:ACSR810m㎡、素導体間隔:400mm
ⅱ.直線スリーブ
電線は、製造工場で通常1~2Km内外の長さで製造され、各現場へ運搬するときは、ドラムに巻いて届けられる。
ⅲ.引留クランプ
電線を支持物に引き留めるには、がいし装置を介して支持物に留めるが、電線をがいし装置に繋ぎ、固定する金物として、次の3種類がある。
ボルトで締め付け固定する金物:ボルト締め付けクランプ
楔効果で固定する金物:楔式クランプ
電線にパイプ状の金物を被せそのパイプを断面中心方向に圧縮して電線を固定する金物:圧縮引留クランプ
一般に、ボルト締め付けクランプ、楔式クランプは「がいし装置」として区分し、圧縮引留クランプは電線付属品として区分しているが、ここでは一括して電線付属品として説明する。
a.圧縮引留クランプ
圧縮引留クランプは、鋼芯線とアルミ線を別々に圧縮する構造になっている。
準備として、引留クランプのアルミ本体部分を当該引留箇所の電線に被せ、電線に挿入しておく。
圧縮引留クランプは、施工に際し必ず電線を切断するので、次に述べるボルト締め付けクランプおよび楔式クランプに比べ、現場作業は増える。
b.楔(くさび)式クランプ
次に、電線をボルトで締めたり、楔効果で固定する金物、すなわちボルト締め付けクランプ(注参照)および楔式クランプについて説明する。
まず、楔式クランプは、右図のように楔金具を電線に装着して、電線が架線による引っ張り力で滑り抜けようとする力に対し、楔効果で電線を締め付け固定するものである。
c.ボルト締め付けクランプ
ボルト締め付けクランプは、金物で電線を挟み、その金物をボルト・ナットで締め付け、電線を固定する。OBクランプ 」と呼ぶことがある。これは、当初、この方式のクランプがアメリカの「Ohio Brass Company」で製造された品物を輸入して使用されたため、会社名を略し「OBクランプ」と言ったのが、現在に至っている。
ⅳ.ジャンパ装置
耐張がいし装置の支持物で、左右径間の電線を引き留めているクランプの間を電線で接続するが、この電線を「ジャンパ線」という。各種のジャンパ装置 が開発・使用されている。
3.がいし設計Insulators design
(1)電気的性能The electrical performance of insulators
がいし設計は、常時の運転電圧、地絡事故時の異常電圧および発変電所での遮断器開閉時の異常電圧(開閉サージ電圧)などに耐え得るよう行う。
塩害対策設計
最近の火力発電所は大量の冷却水を必要とすることと、燃料搬入の便を考え、海岸に建設されることは周知の通りである。
台風の急速汚損に対しては、想定等価塩分付着密度(250mm懸垂がいしの下面(但し中心部は除く)への付着)は海岸~3kmで最大値は0.5mg/c㎡、海岸から遠くなるにしたがって次第に少なくなり、50km以上の地域で0.06mg/c㎡のデータが得られている例がある。
また、平常時の累積汚損では、海岸~1kmで最大値は0.5mg/c㎡、海岸から10km以上の一般地域で0.06mg/c㎡のデータが得られている例がある。
このように、台風の急速汚損は平常時に対して5倍以上内陸まで達しているのが分かる。
想定塩分付着密度0.06mg/c㎡地域では、がいしの設計耐電圧は10.3kV/個、がいし連結個数は16個(287.5/√3=166kV対応)となり、
一方0.5mg/c㎡地域では6.8kV/個に低下して必要連結個数は25個に増加する。
さらに、海岸近傍でしぶきがかかる地域では、懸垂装置の場合、がいしの設計耐電圧は5.0kV/個まで低下し、がいし連結個数は34個と大幅に増加する。
なお、500kV送電線については、設計対地電圧として1線地洛時の健全相対地電圧について常規対地電圧の1.2倍を採っている。
アークホーンの設置
落雷時の雷電圧に耐えられる設計は不可能で、閃絡(フラッシオーバ)を前提として、フラッシオーバ時に設備(がいし・電線)に被害を生じないようにするため、我が国ではほとんどの送電線にアークホーンという金具(電極)を設置している。
逆フラッシオーバ
送電線路で発生するフラッシオーバは、雷が 電線に落雷して電線の電位が上昇し、がいし連またはアークホーン間でフラッシオーバが起こり雷電位は鉄塔を伝わって大地に流れるが、逆に鉄塔または架空地線に落雷して電位が上昇して、鉄塔アームと電線間あるいは架空地線と電線間でフラッシオーバが発生する現象を逆フラッシオーバ言う。
絶縁間隔
送電線の絶縁間隔には、標準絶縁間隔、最小絶縁間隔および異常時絶縁間隔の3種類がある。
「標準絶縁間隔」は、落雷に対応して設けられるもので、がいし連が静止している状態では、落雷時に必ずがいし連でフラッシオーバさせ、電線鉄塔間などではフラッシオーバさせないように絶縁間隔を確保するように設けた間隔である。
「最小絶縁間隔」は、内部異常電圧(開閉サージ電圧swiching surge voltage)に対して十分な絶縁間隔を確保するもので、台風などの強風時に電線が横振れ(超高圧送電線では横振れ角45°、それ未満の送電線では55°)した場合でも保持すべき間隔である。
「異常時絶縁間隔」は、最小絶縁間隔が比較的発生頻度の高い風速に対して対応するのに対し、異常時絶縁間隔は想定最大風速(40m/s)に対してがいし連やジャンパ線が横振れした時に保持すべき間隔で、その線路の最高許容電圧(対地)に対し、注水耐電圧でチェックすることが奨励されている。
クリアランス設定
送電線では、電線およびがいし装置と、支持物との間の絶縁が対地絶縁の最低箇所となり、それ以外の箇所では落雷時のフラッシオーバをさせないように必要な絶縁間隔を確保させるため、クリアランスダイヤグラムを作図して充電部と支持物との間のクリアランスを決定する。
(2)機械的性能The mechanical performance of insulators
がいしは電線を支持物に吊す、または引き留める役割を持つので、電気的性能と同時にこの機械的性能の両方を満足させなければはならない。
(3)がいしの選定The choice of the kind of insulators
がいしには、次のような種類がある。・磁器がいし ・強化ガラスがいし ・有機がいし
ⅰ.磁器がいし
a.ピンがいし
右の写真は66KV鬼怒川線に使用されたピンがいしである。東京電力・電気の史料館 」には、この他貴重な資料が多数ある。
b.懸垂がいし
写真の白がいしはクレビス・アイ型
茶がいしはボールソケット型
磁器がいしのうちでも、最も使用されているのは懸垂がいしであり、その種類は次の通りである。
250mm懸垂がいし(磁器直径254㎜・高さ146㎜)・強度:120KN(クレビス・アイ型)、および165KN(ボールソケット型)
280mm懸垂がいし(磁器直径280㎜・高さ170㎜)・強度:210KN(ボールソケット型)
320mm懸垂がいし(磁器直径320㎜・高さ195㎜)・強度:330KN(ボールソケット型)
340mm懸垂がいし(磁器直径340㎜・高さ205㎜)・強度:420KN(ボールソケット型)
380mm懸垂がいし(磁器直径380㎜・高さ240㎜)・強度:530KN(ボールソケット型)
通常はこれらの懸垂がいしを送電電圧に応じ、複数個直列に接続し、電線の張力に応じ複数個並列に並べ、金具を用いて一体の装置となし支持物と電線間に設置する。
c.耐塩懸垂がいし
耐塩(スモッグ)懸垂がいしは、標準懸垂がいしに比較してひだを深くし、塩分を含んだ大気をひだの奥まで到達し難くし、がいし下面のひだ表面に塩分を付着させ難いように配慮したがいしで、がいし全体の表面漏洩距離を多くし、耐塩特性を向上させたものである。
d.長幹がいし
長幹がいしは、ひだが浅く雨洗効果が大きく、塩害対策地域で使用すると効果がある。
e.ラインポストがいし
ラインポスト(LP)がいしは、鉄構や床面に垂直に固定する構造になっている。
ⅱ.強化ガラスがいし
ガラスがいしは、我が国ではほとんど使用されず、主に欧米で使用されている。東京電力・電気の史料館 」に展示されているもので、我が国ではあまり見ることの出来ない貴重ながいしである。
東京電力管内では、66KV高崎線、66KV上信線、および伊東線などのごく一部に試験的に使用されている。
ⅲ.有機がいし
有機がいしは、ごく最近になって開発され、約100年の歴史がある磁器がいしに比較し、使用実績はまだ浅く、長期間に亘る信頼性は確立されていない。
(4)がいし装置Insulators device
現在最も多く使われているがいしは「懸垂がいし」であるが、がいし1個で絶縁性能を得るのは無理で通常は直列に複数個つなげる。また、電線の張力に応じ、並列に2列(連という)または3列(連)使用することが多い。
ⅰ.懸垂装置
a.直吊懸垂装置
直吊懸垂がいし装置は、主に送電線路の直線箇所で、水平角度荷重が加わらない箇所に用いられる。しかし、わずかな水平角度箇所にも、常時振れっぱなしの形態で使用される。
1連懸垂がいし装置
2連懸垂がいし装置
b.V吊懸垂装置
V吊懸垂がいし装置は、電線把持部が横振れをしないため、直吊装置に比較し電線と鉄塔との間の水平間隔を狭くすることが出来るので、電線路の線下幅(左右回線の水平間隔)を狭く設計でき、結果的に用地幅を狭くすることが出来る。
ⅱ.耐張装置
耐張がいし装置は、・線路の水平角度が多い箇所 ・始点、終点などの引留鉄塔箇所 ・技術基準で耐張型支持物が必要な箇所 ・谷底に支持物が建ち前後径間の電線が引き上げ状態の(垂直荷重の加わらない)箇所など懸垂装置が適用できない箇所
1連耐張がいし装置
2連耐張がいし装置
3連耐張がいし装置
4連耐張がいし装置
ⅲ.ジャンパ支持装置
・直吊懸垂型ジャンパ支持装置 ・V吊懸垂型ジャンパ支持装置 ・長幹支持がいし装置 各種のジャンパ装置 参照)
ⅳ.特殊装置
a.セミストレーン装置
セミストレーンがいし装置は、懸垂形鉄塔で使用される。
b.アームがいし装置
アームを絶縁体のがいし装置で構成し、電線幅および電線の垂直間隔を狭め、コンパクトな設備設計とするときに使用する。
c.タイダウン装置
タイダウン装置は、山岳地で前後径間の高低差が激しい谷間の鉄塔では両径間の電線が引き上げ状態となり懸垂装置が浮き上がる箇所、および直吊懸垂がいし装置を設置すると、線路の水平角度が大きく、がいし装置の常時振れ角度が大きくなり絶縁間隔が保持できない箇所などに、下アームに向かってがいし装置を設け、正常な状態を保持する装置である。
d.バランス耐張装置
バランス耐張装置は、当初は懸垂型鉄塔として建設されたが、時代と共に何らかの理由で電線地上高が不足し、ほぼ懸垂がいし装置の高さ分だけ電線を嵩上げしたいとか、あるいは塩害対策上がいしを増結したいが絶縁間隔が不足する等の理由から適用される。
右はバランス金具のクローズアップ写真である。
4.支持物基礎設計Designs of foundations of Support
上部構造物から受ける重力方向の圧縮荷重、や反重力方向の引上荷重に耐え得る構造とする。
基礎の種類と概要図
基礎は、上記の各種基礎に対して鉄筋コンクリートを用いた基礎が主に使われているが、その主な形状は、右の「基礎の種類と概要図」に示す通りである。
(1)直接基礎General foundations
ⅰ.逆T字型基礎
「逆T字型」基礎は、「T」の字を逆さにした形状で、掘削した穴に逆T形の鉄筋コンクリート構造体を作る。
ⅱ.オーガコンクリート基礎
大口径オーガ機械で比較的良質な地山を削孔し、穴の中へ鉄筋かごを挿入し、コンクリートを打設して基礎体を構築するものであるが、あまり多くは用いられていない。
ⅲ.べた(マット)基礎(つなぎ梁基礎、門型基礎)
4脚又は2脚の基礎床板を一体化して上部構造を支持するもので、地盤が軟弱な箇所で、基礎底面接地圧を減少させると共に、不同沈下による上部構造への悪影響を阻止する目的で使用される。
また、主に河川敷内に建設する場合に用いる「門型基礎」(右写真)もこの分類に入る。
ⅳ.鋼材基礎
一時的な仮工事などの短期間だけ使用する基礎には、建設・撤去が簡単にできるため、鋼材を基礎床板に敷くだけの構造の基礎が用いられることがある。
ⅴ.直埋基礎
鉄塔基礎材を地山に直接埋設しただけの基礎で、耐力はほとんど期待できないので、送電線草創期の明治大正時代の規模が小さい鉄塔に用いられていたが、現在では使用されていない。
(2)杭基礎Pile foundations
水田、砂地など、地盤が軟弱な地質の場所で、「逆T字型」などの直接基礎では圧縮荷重に対し地耐力が期待出来ない場所に使用するもので、基礎の床版の下方に地耐力が期待出来る地層まで杭を打ち、圧縮荷重に耐えるようにしたものである。
ⅰ.木ぐい基礎
杭の材料として昔は松杭などが使用されたが、現在では鋼管杭またはコンクリート杭などが使用されており、ほとんど使用されていない。
ⅱ.既製コンクリート杭基礎
製作した杭を現地に運搬して杭打機で打ち込み使用する。
ⅲ.木ぐい基礎
上記のコンクリート杭の代わりに鋼材を使用したもので、上記と同様、環境に与えるデメリットからあまり使用されていない。
ⅳ.木ぐい基礎
最近は小型で効率の良い騒音振動対策を施した削孔機が開発されており、それで掘削した穴に現地でコンクリートを流し込み鉄筋コンクリート柱を造る、いわゆる「場所打ち杭」工法が盛んに用いられる。
(3)ピア基礎Pier foundations
ⅰ.深礎基礎
深礎基礎は、大きな荷重が加わる基礎で傾斜が急な山岳地斜面に建設する場合など、「逆T字型」基礎では急斜面で引き上げ荷重に対して基礎床版上部の土の重量が期待出来ない場所、などに適用する。
ⅱ.井筒基礎
この基礎は、軟弱地盤で湧水が多く、他の工法では施工困難な場合に適用される。
ⅲ.ニューマチックケーソン基礎
本工法は、井筒底部に気密室を設け、圧縮空気によって内圧をかけ、内部への湧水を防ぎながら掘削を行うものである。
(4)アンカ基礎Anchor foundations
本基礎は、逆T字型基礎、べた基礎と組み合わせて使用するものである。
ⅰ.アースアンカ基礎
地盤にアンカ(鋼棒)を施工し、アンカと地盤のせん断力または付着力によって引き上げ力に抵抗させ、圧縮に対しては、地盤の圧縮耐力に期待するものである。
ⅱ.ロックアンカ基礎
岩盤にアンカ(鋼棒)を施工し、アンカと岩盤のせん断力または付着力によって引き上げ力に抵抗させ、圧縮に対しては、岩盤の圧縮耐力に期待するものである。
5.上部支持物設計(鉄塔)Steel towers designs
ここでは鉄塔に限って説明する。
塔体
塔体は、本項で以下に述べるように細長い鋼材を組み合わせ、一般に四角形の断面を持ち、その高さは低いもので10m程度から高いもので東京タワーより高い鉄塔高346.5m(「世界記録・日本記録」参照 )まである。
鉄塔の風圧荷重、および電線・地線・がいしの風圧荷重
電線の張力による荷重として水平角度荷重・垂直角度荷重、不平均荷重、電線断線時の不平均張力およびねじり力
鉄塔・がいし・電線の重量による荷重
があり、鉄塔の高さ、種類(懸垂型、耐張型、引留型等)毎に詳細な計算手法が定められている。
腕金(アーム)
送電線の電圧階級により、「電気設備の技術基準」に基づいた地上高に電線を張るために必要な高さの塔体位置から水平に鋼材を伸ばし、高い電圧が荷電されている電線と塔体間を短絡させないようにして、その先端にがいし連を介して電線を固定するための設備である。ⅱ.全体形状による分類-a.標準形を参照 )
(1)材料Steel tower materials
送電鉄塔は、一般に細長い鋼材を組み合わせ、十数m~数十m上空に張る電線を支える構造物である。
ⅰ.等辺山形鋼
等辺山形鋼は、細長い棒状の鋼材で、断面は二等辺三角形の底辺が無い2辺で、「く」の字形状をしている。・辺の幅45㎜・厚さ4㎜~辺の幅250㎜・厚さ35㎜
ⅱ.中空鋼管
中空鋼管も細長い棒状の鋼材で、その断面は名前の通り中空の筒状であり、使用するときは座掘強度を高めるため中空の部分にモルタルまたはコンクリートを流し込んで使用することもある(次項「MC鋼管」で解説する)。
右の写真は、山岳地に建設されたUHV(100万V設計)送電線の巨大な主柱材・基礎立ち上がり部分である。
ⅲ.MC鋼管
中空鋼管の座屈強度を高めるため、中空の部分にモルタルまたはコンクリートを隙間無く充填するMC鋼管は関西電力で多く使用されている。
(2)形状Shapes of the steel towers
鉄塔は、上記の等辺山形鋼または中空鋼管を使用し、荷重がかかる部分は必ず三角形構造(ラーメン構造の鉄塔は除く)とし、各鋼材(部材)には圧縮または引っ張り荷重だけが加わり、曲げ・ねじり荷重はほとんど加わらないように組み合わせ、各鋼材を複数個のボルト(直径16~42㎜)で接続して組み立てる。
ⅰ.塔体骨組み構造による分類
シングルワーレン構造
ダブルワーレン構造
Kトラス構造
プラット構造
ブライヒ構造(現在最も多用されている)
ラーメン構造
耐雪構造(積雪地帯の最下部構造として使用されている)
現在最も多く使用されている骨組み構造は、「ブライヒ結構」 である。66KVからUHV送電線に至るまでほとんどの送電線でこの構造のものが用いられている。各鉄塔とも、主に塔体中間部より下部に用いられている。
ⅱ.全体形状による分類
a.標準形
(四角形断面、電線配列は3段アームで左右対称に1回線づつ垂直配列、架空地線が2条のものは4段アームとなる)
b.多回線標準形
(標準型の4回線以上の多回線鉄塔)
c.片側垂直配列形
(狭いルート幅しか確保出来ない場所に適用)
d.えぼし形
(着氷雪地帯で、スリートジャンプ事故回避のため適用、電線配列は1回線水平配列)
e.ドナウ形
(鉄塔高を低減したい箇所に適用、電線配列は左右対称に2段アームで、上アーム1条および下アーム2条水平配列)
f.矩形(長方形)
(鉄塔高を低減する箇所、その他特殊箇所に適用)
g.門形
(鉄道軌道上の送電線に適用)
h.三角形
(三角形断面。塔体を三角形状にして四角形鉄塔より主柱材を1本減らすことで、鉄塔重量が低減できたり、基礎工事量を低減させ得る設計条件の箇所で、建設工事費が軽減できる箇所に適用。三角形状は、正三角形または二等辺三角形。)
(3)使用目的による分類The classification by the purpose of use
支持物を使用する目的で分類すると、次の通りとなる。
標準形の説明
懸垂形 は、垂がいし装置(直吊、V吊等)を使用した鉄塔である。
直線鉄塔
線路の水平角度が全くない直線箇所に用いる。
角度鉄塔
線路の水平角度がある箇所に用いる。
耐張形 は、耐張がいし装置を使用した鉄塔である。
直線鉄塔
線路の水平角度が全くない直線箇所に用いられる。
角度鉄塔
水平角度のある箇所に用いられ、耐張形の代表的使用例として挙げられる。
引留鉄塔
線路の始端または終端変電所引き込み箇所あるいは電線架線設計条件が前後径間で異なり、常時アンバランス張力が加わる箇所等(前後径間で電線種別、導体方式が変わる箇所など)に用いる。
保安鉄塔
線路の直線部分で、懸垂鉄塔が連続する場合に補強目的で用いたり、前後径間の径間長の差が大きく、不平均張力が加わる箇所に用いるもので、補強設計を施した鉄塔である。
軽保安鉄塔 :懸垂形を10基以上連続して使用する場合には、10基以下ごとに補強のためこの鉄塔を設ける。また、前後径間の径間長の差が大きく軽度の不平均張力が加わる箇所に用いる。重保安鉄塔 :長径間と、それに隣接する径間との間には、不平均張力が生ずるが、そのような大きな不平均張力が加わる箇所に適用する。
特殊形の説明
長径間箇所、海峡または河川横断箇所、撚架箇所、分岐箇所、および引き回し箇所等で、標準形が使用できない特殊箇所に使用する鉄塔を全て特殊形として分類する。特殊な・めずらしい形の送電線 」の「ワンポイント特殊設計箇所 」に掲載した鉄塔は、矩形鉄塔、1回線水平配列鉄塔および錘付懸垂鉄塔などを除き、「特殊形」に分類される鉄塔である)
以上のように送電鉄塔にはいろいろな分類の仕方があり、電圧の違いで小型のものから大型のものまで、多種多様の形の鉄塔が建設されている。